
クリニックからのお知らせ
新宿・歌舞伎町|双極性障害の「躁のあと」のだるさ対策
双極性障害の「躁のあと」に続くだるさ・疲労をやさしく解説
当院は新宿・歌舞伎町の夜間診療に対応する精神科です。双極性障害(躁うつ病)は、気分が「上がりすぎる(躁・軽躁)」時期と「落ち込む(うつ)」時期をくり返す病気。治療は薬物療法に加え、生活リズム調整(IPSRT)や家族支援などの心理社会的療法を組み合わせるのが標準です(詳しくは下部「参考リンク」)。
なぜ「躁のあと」にだるさが続くの?
症状が落ち着いても、生活機能(体力・集中力・睡眠)の回復は遅れやすいことが知られています。夜型生活や不規則な勤務、飲酒の影響で回復がさらに遅れることも。焦らず、段階的に整えることが近道です。
今日からできる:だるさ対策の7ステップ
1) 起きる・寝る・食べる・出勤の時刻を±30分で固定
社会リズム(IPSRT)の考え方です。まずは起床時刻の固定から。就寝前は強い光・スマホ・カフェインを控えます。
2) 朝は明るい光、夜は暗く静かに
起床直後はカーテンを開けて光を浴び、夜は照明を落とします。体内時計の再同期が進み、睡眠の質が上がります。
3) 仕事・運動は10〜20%ずつ段階的に
「一気に取り戻す」は反動の原因。週ごとに少しずつ活動量を増やし、無理をしない計画で。
4) お酒とカフェインを作戦的に
飲酒は睡眠を浅くし翌日の倦怠感を悪化させます。飲む日・量・終了時刻を事前に決めて少しずつ減らしましょう。カフェインは起床後〜午後早めまでに。
5) 水分と軽い補食を“昼に寄せる”
夜型の方は朝昼の栄養が薄くなりがち。水分+たんぱく質+複合炭水化物の軽食を日中に。血糖の乱高下を避けるのがコツです。
6) 服薬は最小有効量+副作用チェック
強い眠気・だるさが出る場合は、内服時間の調整や薬剤変更を主治医と相談を。維持療法は再発予防の柱ですので、自己判断の減量・中止は不可です。
7) マインドフルネスは短く・こまめに
- 3分呼吸法(1分姿勢・1分呼吸・1分全身)を1日数回
- 衝動サーフィン(飲酒や夜更かし衝動を90秒観察)
- ボディスキャン(就寝前5分=入眠儀式)
※薬の代替ではありません。睡眠時間を削って行わないのがポイント。
早めの受診が必要なサイン
- 活動量が急に落ちる/過眠または不眠が続く
- 楽しめていたことに興味がわかない日が続く
- 飲酒量が増える、出勤できない日が増える
こうした変化が数日〜1週間続くときは、うつへの遷移の可能性も。
当院ができるサポート(夜間・歌舞伎町)
- 生活リズム(IPSRT)+睡眠の整え方を夜型生活・シフト制にも合わせて個別設計
- 薬に頼りすぎない計画(最小有効量を目指し、副作用を評価)
- 就労・学業配慮の診断書作成、自立支援・手帳のご案内
- お酒との付き合い方、回復ペース配分のコーチング
よくある質問(FAQ)
薬をできるだけ減らしたいのですが?
再発予防のため薬物療法は重要ですが、症状と再発歴を踏まえ最小有効量を目指します。生活リズム介入やマインドフルネスを補助として併用します。
マインドフルネスだけで良くなりますか?
単独の主治療ではありません。不安や残遺症状の軽減などが期待され、薬物療法・生活調整と組み合わせるのが基本です。
どれくらいで体力は戻りますか?
個人差がありますが、機能回復は症状の回復より遅れがち。ムリを避け、活動量を10〜20%ずつ段階的に増やす計画が結果的に近道です。
参考リンク
- NICE:双極性障害の評価とマネジメント(CG185)
- CANMAT/ISBD 2023:双極性障害治療ガイドラインの要約と最新エビデンス
- IPSRTの有効性レビュー(2020, Open Access)
- MBCTのRCT(12か月追跡)Perich 2013
- 躁エピソード後の機能回復の遅れ:Tohen 2000
※本ページは医療情報の提供を目的としています。個別の診断・治療は診察で決定します。体調急変時は速やかに医療機関へ。
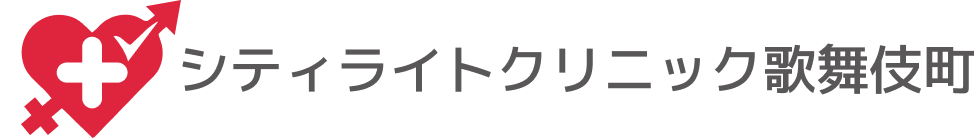
 03-6265-9265
03-6265-9265